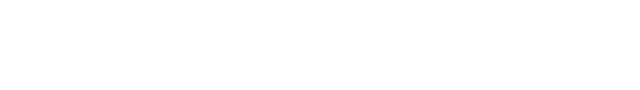骨粗鬆症
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の強度が低下し、ちょっとした転倒やくしゃみなどでも骨折してしまうリスクが高まる病気です。特に高齢の女性に多く、閉経後の女性ホルモン(エストロゲン)の低下が影響するといわれていますが、最近では男性の骨粗鬆症も増えてきています。
当院では、骨粗鬆症の早期発見・早期治療に力を入れております。骨密度検査をはじめ、生活習慣病や内服薬との関連性も丁寧に確認しながら、その方に合った治療プランをご提案しています。JR北浦和駅から徒歩10分の羽尾内科医院では、通いやすさも含めて継続したケアが可能です。
骨粗鬆症の症状について
骨粗鬆症自体は、初期にはほとんど自覚症状がありません。そのため「サイレント・ディジーズ(静かな病気)」とも呼ばれます。ですが、以下のような症状が出た場合は、すでに進行している可能性もあります。
-
背中や腰の痛み(特に起床時や長時間座った後)
-
身長の縮み(若い頃より3cm以上低くなっている)
-
背中が丸くなってきた
-
つまづきやすくなった、ちょっとした転倒で骨折した
特に背骨や手首、大腿骨の骨折は、日常生活に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。
骨粗鬆症の原因について
骨粗鬆症の主な原因は、以下のように多岐にわたります。
加齢やホルモンバランスの変化
-
閉経後のエストロゲンの減少
-
高齢による骨代謝の低下
栄養・生活習慣の影響
-
カルシウムやビタミンDの不足
-
タバコや過度のアルコール
-
運動不足
病気や薬の影響
-
糖尿病や甲状腺疾患
-
ステロイド薬の長期使用
-
慢性腎疾患 など
これらのリスク因子(=病気の発症に影響する要因)を組み合わせて評価することが、骨粗鬆症の早期発見に役立ちます。
骨粗鬆症の種類について
骨粗鬆症にはいくつかの種類があります。
-
原発性骨粗鬆症
- 加齢や閉経などが原因で発症します。特に閉経後女性に多いです。 -
続発性骨粗鬆症
- 他の病気や薬剤(ステロイドなど)が原因で起こります。 -
特発性骨粗鬆症
- 若年者に発症し、原因が明確でないケース。まれですが注意が必要です。
それぞれで治療や予防法が異なるため、医師による適切な診断が重要です。
骨粗鬆症の治療法について
骨粗鬆症の治療には、薬物療法と生活習慣の改善が柱となります。
薬物療法
-
ビスホスホネート製剤(骨の吸収を抑える)
-
デノスマブ(抗RANKL抗体、半年に一回の注射)
-
活性型ビタミンD
-
ホルモン療法(女性の場合)
食事療法
-
カルシウム(牛乳、ヨーグルト、小魚など)
-
ビタミンD(鮭、きのこ類、日光浴)
-
ビタミンK(納豆、青菜)
運動療法
-
軽い筋トレやウォーキング
-
バランス運動(転倒予防)
当院では、骨密度検査の結果や既往歴、現在の体調をふまえて、患者さんに最も合った治療法をご提案しています。服薬だけでなく、生活の中でできる工夫も一緒に考えていきます。
骨粗鬆症についてのよくある質問
Q1. 男性でも骨粗鬆症になりますか?
A1. はい、なります。女性に多い病気ですが、加齢や生活習慣により男性も発症します。特に高齢の男性は注意が必要です。
Q2. 検査は痛いですか?
A2. いいえ。骨密度検査は短時間で済む非侵襲的な検査です。痛みはありません。
Q3. 治療を始めたら骨は元に戻りますか?
A3. 一度スカスカになった骨を完全に戻すことは難しいですが、骨折リスクを大幅に減らすことは可能です。「寛解(かんかい)=症状が落ち着く状態」を目指す治療になります。
院長より
当院では、循環器専門医として心臓や血管の病気を診ることに加え、生活習慣病やその影響で起こる骨粗鬆症にも力を入れています。
骨粗鬆症は、「年のせい」で片づけてしまいがちですが、放置すると生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。特に転倒による骨折で寝たきりになる方も少なくありません。
私たち羽尾内科医院では、骨粗鬆症の早期診断・治療・予防に積極的に取り組んでおり、女性医師による丁寧な対応もご好評いただいております。北浦和駅からも徒歩圏内で、駐車場も8台分完備しておりますので、お気軽にご相談ください。